根性論は間違いだったのだろうか?

昭和の東京オリンピックから30年もの間、スポーツ業界からビジネスの現場の主流だった根性論。
「気合が足りん!」
「営業は100回足を運んで1件取れたらいいんだ!」
「水を飲むな!休むな!根性がつかないぞ」
まるで、映画で見る第二次世界大戦時代のことかと思ってしまうのですが、紛れもなく20年ほど前まで世の中を支配していた根性論という考え方のことです。
そして今は、間違いだったことが明らかになっています。
根性論とは?

根性論(英: die-hard spirit, never-give-up spirit)は、昭和中盤から平成の終わりまでに広まり、今もわずかに残る精神論の1つです。
根性論のはじまり
根性論の始まりは、1964年の東京オリンピックで大活躍された女子バレーボール日本代表「東洋の魔女」が始まりとされています。
厳しい練習と気持ちを強く持つことで、当時の東京オリンピックで金メダルを獲得されました。
東洋の魔女の快挙は、スポーツ業界で盛んに研究され「勝利という目標達成のために精神を集中し、困難に屈せず継続する強固な意志」と定義された根性はスポーツのみならずビジネスや教育の場にも広まることになります。
努力=気持ちを保つ
また、根性論の中では盛んに「努力」という言葉がセットで使われます。
努力(英:perspiration)は、本来は結果を得るための過程を工夫する意味があるのですが、日本国内では長らく「気持ちを保つ」という意味で使われていました。
とにかく努力の量
根性論に努力が加わったことで、努力の量を重ねることが重要視されるようになります。
そしていつしか、「努力を重ねる→根性が強くなる→結果が出る」という認識は日本国内に広く広まってしまいます。
スポーツの場では、体をとにかく痛めつけること、水を飲まずに頑張ることとどんどん過激な方向へ…。
ビジネスの場でも、「24時間働けますか」のように「とにかく努力の量」を増やすことで結果を出す根性論が広まってゆきます。
根性論が通用しなくなる現実
1960年代に始まり、高度経済成長期からバブル景気もあって成功する方も増えた根性論ですが、バブル崩壊後の1990年代からは偏った考え方が見直されるようになります。
それは、根性論が通用しなくなる現実が訪れたからです。
「毎年ベスト4まで行けても全国大会に進めない強豪校」
「国内では有力でも国際大会で勝てないチーム」
「今までのように仕事をこなしても減り続ける成果」
スポーツやビジネスの場で、「もしかしたら根性論は間違っていたりして」と疑問を持つ方が増えてきます。
長く続けているなら尚更です。
「今日と同じ明日があると思うなよ」だ。「今日とまったく違う明日がやってくる」のだ。変化の波に乗るか、波に溺れるか。どうせなら、波に乗り風に乗り、まったく新しい世界を楽しみたいじゃないか。
堀江貴文『ゼロからはじめる力〜空想を現実化する僕らの方法』はじめに p3
根性論は1960年代から1990年代まで続いていましたが、その間に世の中は少しずつ変わって、30年間も経つと全く別の世界のように変わっています。
疑問を持つ方が増えると、根性論の良くない面が注目を集め、「根性論は危険」「デメリットの多い時代遅れな方法」と思われるようになります。
論理的なトレーニング

根性論が否定されるようになってから、スポーツ業界では論理的(英:logic)なトレーニングが取り入れられ、ビジネスでは新しいビジネスモデルが採用されるようになります。
論理的なトレーニングは、ロジカルシンキングとも呼ばれる論理的思考に基づいています。
科学的な理由を求める
論理的なトレーニングでは、科学的な理由が求められます。
例えば、足の筋力をつけたい時には根性論では「ひたすらうさぎ跳びをする」となってしまいますが、筋力アップに必要な運動の量、さらに筋肉を大きくするために必要な栄養まで細かく決まっています。
甲子園の強豪校では、専門の管理栄養士さんが選手の食事を管理しているところもあるほどです。
成功している人に学び成功体験を重ねる
また、成功している人の良いところを真似て、正しい方法を行うことも大切にされています。
野球のバッティングを上達するために、根性論では「素振りを100回」こなすところを、大谷翔平選手のフォームを動画で見て、自分のフォームを改善し、その結果が得られたかといった方法です。
失敗を重ねて、たまたま得られた成功を成果とするのではなく、成功しやすい方法で成果を得るほうが短期間で上達もし易いとされています。
論理的なトレーニングのは何が得られたかの成果
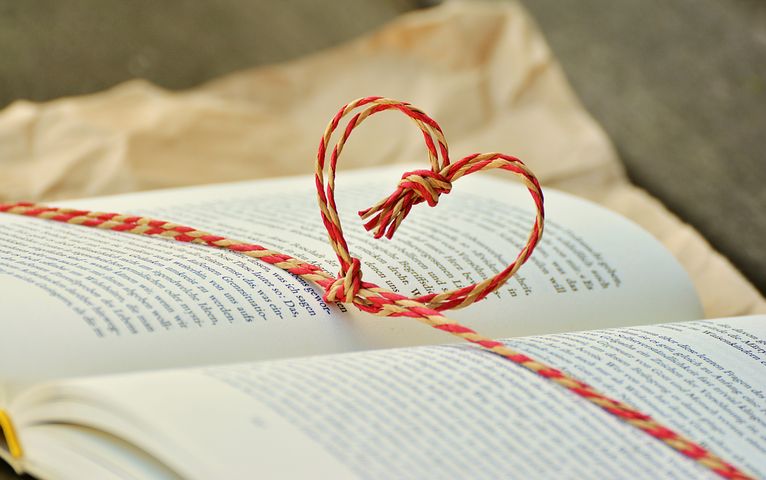
論理的なトレーニングの「成果」は、科学的な理由を元に成功体験を重ね、努力の質を大切にしています。
それでは、何をもって成果とするのでしょうか?
それは、「何が得られたか」の変化です。
得られたものが優勝や金メダルなら、最高の結果といえます。
ただ、バッティングフォームが良くなりヒットが増えた、競泳のベストタイムを更新した変化も立派な成果です。
ただ、「頑張っていたのに…」と努力の過程が評価されないのは論理的なトレーニングの厳しい点でもあります。
結果を大切にするという点では、成果主義の1つでもあるのかもしれません。
www.yu-hanami.com
www.yu-hanami.com
参考にした本はこちらです
葛西紀明『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』
www.yu-hanami.com
平井伯昌『見抜く力―夢を叶えるコーチング』
見抜く力―夢を叶えるコーチング (幻冬舎新書)
堀江貴文『ゼロからはじめる力〜空想を現実化する僕らの方法』
www.yu-hanami.com
三輪祐範、幸田露伴『超訳 努力論』
www.yu-hanami.com
鈴木博毅『 シャアに学ぶ“逆境”に克つ仕事術』
www.yu-hanami.com
