根性論が道を間違えた理由

「根性が足りん!」
「たるんどる、腕立て伏せ100回」
「努力は裏切らない、とにかく頑張れ」
こんなことを言いながら、監督やコーチが竹刀を振り回し選手を追い立てる。
令和の現代なら、警察に通報されるような光景です。
ですが、ほんの数10年前までは、スポーツのトレーニングというと珍しくはない光景でした。
根性論(英: die-hard spirit, never-give-up spirit)と呼ばれる、未だに名残が残る考え方です。
根性論が通用しなくなった時代

1960年代が起源といわれ、バブル景気が崩壊する1990年代まで日本国内で広まっていた根性論。
長らく日本のスポーツ業界とビジネスの現場の主流だった根性論は、時代の変化に乗ることができず「危険な方法」「効率が悪い」と今では否定されるようになりました。
根性論に頼らないアスリートの方が大きな成果を上げる一方で、根性論が元で事故が起こり、人の命に関わる危険性が明らかになったからです。
根性論には僅かなメリットもあった

現代では通用しなくなり、危険な方法といわれる根性論が全て間違っていたわけではないと思います。
ほんの僅かですが、根性論にもメリットはありました。
基礎を身に着けるには最適
根性論の「何を“どのくらい”行ったか」で努力の量を大切にすることは、物事の基礎を身につけるには向いている方法です。
ビジネスの現場では、「電話応対の手順」「タイピングの速さ」など、どうしても数をこなさなければ身につかないこともあります。
根性論が道を間違えた3つの理由

根性論が成果を出せず、デメリットばかり残ってしまったのは「思い込み」「努力の量の限界」「切り替えができない」ことにあります。
「思い込み」で成功している人に学べなかった
根性論が道を間違えてしまった大きな理由は、「成功している人に学べなかった」ことです。
試合で負けてしまった相手が「きっと階段登りを100往復しているはずだ」「営業回りを100件行っているのか」と決めつけていました。
「根性論なら成功する」という考え方そのものが、既に古くなった「思い込み」になっていたんです。
現実は変化したのに、それを測る評価基準が古いままの状態。
つまり、もはや「時代遅れ」なのです。
こうなると、当然、失策を重ねていくことになります。
鈴木博毅『 シャアに学ぶ“逆境”に克つ仕事術』p23
「何か秘訣があるのかな」と疑問を持たなかったのは、選手や部下を導く役割の人の責任でしょう。
「努力の量には限界」がある
また、どんなに努力の量を求めても、時間は限られています。
限界を超えてしまうとスポーツでは体を壊してしまい、ビジネスでも過労になってしまいます。
そして、努力の量は根性論が主流だった当時は「皆んなしている」ことでもありました。
単純な努力の量だけには限界があり、練習と休憩のバランスが大切なことは、根性論から現代的なトレーニングへの変化の時代を過ごしたアスリートの方の著者にも書かれています。
私は日ごろから「練習をしすぎない」ための工夫をいろいろしていますが、それの同時に「今日のこたは一切考えない時間」もできるだけつくふように努力しています。トレーニングをしないというだけでなく、スキージャンプそのものを考えない時間です。
中略)
休みの日だからといって、家でゴロゴロしているだけでは、どうしても仕事のことが頭をよぎり、「脳を休ませる」ことができません。
「趣味に没頭する」「家族や友人と出かける」など、仕事のことを考える隙のない環境に身を置くことが大切です。
葛西紀明『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』 p166
「切り替えができない」頑固さ
試合に負けた原因を「相手は100往復の階段登りをしているはずで、うちは半分しかしていなかった」と決めつけず、「それなら別のトレーニングをこなそうか」と切り替えれていたら、根性論はここまで避難されることはなかったはずです。
1度決めたことを途中で変えることが「良くないこと」と考えてい根性論は、基礎から応用へと高度になった世界で「量から質」へと切り替えができない頑固さがありました。
「若さゆえの過ち」すべてを教訓として武器に変えるためには、振り返ることさえ苦しい記憶に、真正面から向き合う必要があります。
心に深い痛みを残した記憶は誰もが目をそむけたくなるもの。
けれど、その苦々しい記憶を冷静に分析して武器とするには痛みから逃げず、自分の弱さを摘出することがまず必要だったはずです。
鈴木博毅『 シャアに学ぶ“逆境”に克つ仕事術』p25~p26
オリンピックやパラリンピックで選手が敗れてしまっても、「切り替えていきましょう」と前向きなコメントをされる解説者がほとんどです。
車いすバスケの日本代表や解説者の方は、相手にボールを取られてもトランジション (英語: transition)とプレーを切り替えることが大切と話されています。
状況が変化しやすい中では、切り替えることはとても大切な意味を持つんですね。
根性論から論理的なトレーニングへ
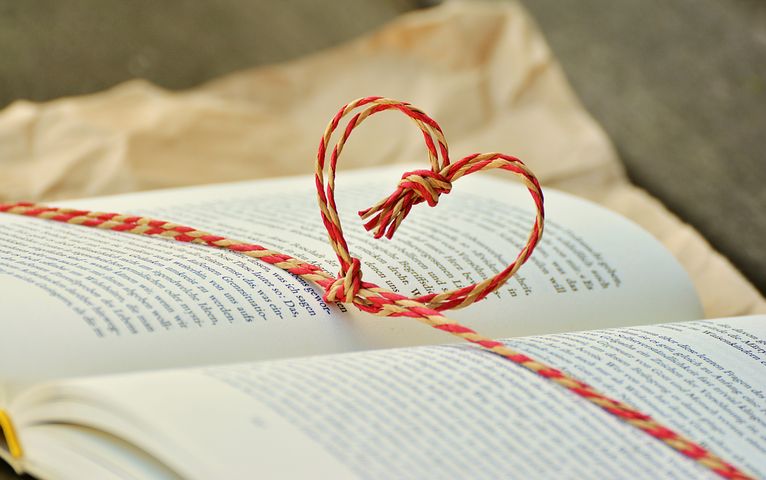
根性論に頼らず、しっかりと原因を見つけ工夫することは、スポーツでもビジネスでも欠かすことはできません。
時代の変化、世界の変化に合わせて柔軟な切り替えができる論理的なトレーニングへと変わった2020年代。
大谷翔平選手を始め世界的なアスリートの方が、時代の変化に乗り、見る人を驚かせてくれるような結果を出してくれています。
何より、笑顔でインタビューにこたえてくれる姿はテレビのこちらまで、取り組んでいることが「好きなんだなぁ」と思いが伝わってきています。
www.yu-hanami.com
www.yu-hanami.com
参考にした本はこちらです
葛西紀明『40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方』
www.yu-hanami.com
平井伯昌『見抜く力―夢を叶えるコーチング』
見抜く力―夢を叶えるコーチング (幻冬舎新書)
堀江貴文『ゼロからはじめる力〜空想を現実化する僕らの方法』
www.yu-hanami.com
三輪祐範、幸田露伴『超訳 努力論』
www.yu-hanami.com
鈴木博毅『 シャアに学ぶ“逆境”に克つ仕事術』
www.yu-hanami.com
