読書感想文の目的は「本を読む機会」と「考えること」
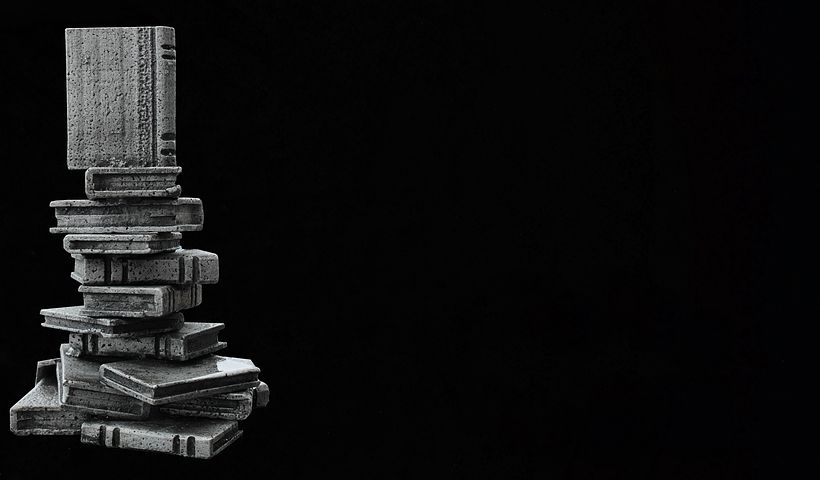
読書感想文は普段から読書の機会がない、学生さんたちには悩みのタネになる宿題ですよね。
電子書籍やWebから簡単に情報が得られる今の時代。
なぜ読書感想文に取り組まなければならないのでしょう?
今回は公的な機関の見解と、花水由宇(hanami yuu)独自の見解をまとめてみましたよ。
読書感想文とは?
読書感想文は、本を読んだ感想を400〜1200文字の文章にまとめる小学校・中学校・高校の長期休暇の課題です。
読書感想文は、「感想」とあるように本を読んで自分が思ったこと、動かされた感情、新しい気付きを文章にまとめます。
内容が著者の紹介や物語の世界観の説明ではなく、あくまで自分の思いや考えが感想文のテーマになっていることが重要です。
読書感想文を書く目的は「本を読む機会」
読書感想文を書く目的は、勉強をしている学校、公的な全国学校図書館協議会という機関でそれぞれの見解を発表しています。
それでも、読書感想文は「何のためにあるの?」と誰もが思うのではないでしょうか?
自称読書家で、ブログやWebライティングで文章を書いている花水(hanami)の見解は1つです。
それは、「本を読む機会」のため。
学生さんは、いずれ社会に出て働くことになります。
多くの職業で文章を「書く」ことは必要な技術ですが、全ての職業で必要なわけではありません。
それでは、「読む」ことは?
こちらは、私の知る限り全ての職業で必要なのではないでしょうか?
「いや、俺は革職人になるから」
「将来はプロスポーツ選手になるから」
中には「家業の漁業を継ぐから」
書き出すときりがありませんが、事務仕事のない職業でも読むことは欠かせません。
革職人の方は、成功している職人さんの書籍やファッション業界の記事から流行を知る必要があるでしょう。
漁業や農業などの一次産業の方も、天候に関する情報や作物の取れ高の情報は専門家の書いた情報を読むことになるでしょう。
ほとんどの仕事で、今これから変化していく情報を得るためには「読む」ことは誰にも必要な技術だと思います。
頭が柔軟で成長の盛んな10代の頃に、「本を読む機会」があることは後々「読む」力を伸ばすためになるはずです。
読書感想文は「読書の習慣」と「考える力」を養うことが目的
読書感想文に取り組む目的は何なのか?
私の考えは「本を読む機会」のためでした。
ここで、公的な機関の見解を紹介します。
学校の目的〜読むことと書くことの勉強
国語科の「第5学年及び第6学年」の教育内容で、「書くこと」の能力を育てるため次のように定めている。
「事象と感想、意見などとを区別するとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりすること」について指導する。
また、「読むこと」の能力を育てるため「書かれている内容について事象と感想、意見の関係を押さえ、自分の考えを明確にしながら読むこと」について指導する。参照) 小学校学習指導要領(平成10年度改定)
小学校では「書く」ことと、「読む」ことの両方の勉強のために読書感想文を取り入れています。
大切なことは「事象」と「感想」の区別とあります。
小説の場合には、「事象」は物語の中で起こった出来事や登場人物の考えに当たります。
「感想」は、物語の中で起こった出来事や登場人物の考えに対する「自分の気持ち」。
物語の中の出来事と現実の自分の気持ちを区別することが大切なのでしょう。
読書感想文で読書の習慣と考える力を養う
子どもや若者が本に親しむ機会をつくり、読書の楽しさ、すばらしさを体験させ、読書の習慣化を図る。
より深く読書し、読書の感動を文章に表現することをとおして、豊かな人間性や考える力を育む。
更に、自分の考えを正しい日本語で表現する力を養う。読書感想文を書く目的は、書くことによって考えを深められるからです。
読書感想文を書くことを通して思考の世界へ導かれ、著者が言いたかったことに思いをめぐらせたり、わからなかったことを解決したりできるのです。
ですから読書感想文は「考える読書」ともいわれます。
また、どんなに強く心を動かされても、時がたてばその記憶は薄れてしまいます。読書感想文は自分自身の記録です。読み返すことによって、いつでも「感動した自分」に出会うことができるのです。
それは、「考える力」を養うことを大切にしているということ。
読書感想文を書く目的で出会った本はあくまできっかけで、「自分がどう思ったのか」が重要ということですね。
読書感想文全国コンクールの受賞作品の共通点
青少年読書感想文全国コンクール受賞作品
小学校高学年の部 戸森しるこ「ぼくたちのリアル」
3人の小学校の夏を描いた「ぼくたちのリアル」。
登場人物の3人の友情だけではなく、作品のテーマになっている「自分の気持ちとの向き合い方」を掘り下げた読書感想文でした。
中学校の部 キャシー・アッペルト「ホイッパーウィル川の伝説」
家族の生と死をテーマにした「ホイッパーウィル川の伝説」の読書感想文。
読書感想文を書いた受賞者の中学校の方は、正直すごいなぁと思いました。
私なら、おそらく家族の大切さにをテーマにすると思います。
受賞者はさらに1歩踏み込んで、家族とのつながりの大切さから、「自分が今を精一杯生きているか?」をテーマに考えをまとめていました。
高等学校の部 江宮隆之「白磁の人」
高校生の方になると、もう作家さんですね。
江宮隆之さんの「白磁の人」は、日韓問題と差別をテーマにした物語です。
受賞者の方は、差別がない世界を理想に思いながらも、ほとんど不可能なことではないかと思いを綴られています。
ですが、差別のない世界は訪れなくても、自分の中でだけ差別を無くして生きることはできる。
差別や偏見を持たない生き方ができたとき、本当に人は穏やかに、そして多くの人に自然と信頼されて生きていけるようになるのではないか?
ここまでの読書感想文となると、プロの作家さんの書評を読んでいるようでしたよ。
「自分の思い」をテーマすること
青少年読書感想文全国コンクールの受賞者の方の作品を読ませていただくと、すごいなぁと思える共通点がありました。
それは、「自分の思いをテーマ」に書いているということ。
作品から受けた考えを元に、自分の思いや考えでテーマを生み出して書いていました。
「本を読む機会」と「考えること」が目的の読書感想文
小学校・中学校・高校の長期休暇の課題、読書感想文。
今回は何を目的に読書感想文があるのかをまとめてみました。
花水由宇(hanami yuu)が考える読書感想文の目的は、「本を読む機会」のため。
後々「読む」力を伸ばすために、頭が柔軟で成長の盛んな10代の頃うちに「本を読む機会」があることは大切です。
青少年読書感想文全国コンクールは多くの学校から応募されています。
コンクールを主催する全国学校図書館協議会の見解では、「考える力」を養うことを大切にしているとあります。
青少年読書感想文全国コンクールの受賞者の方の読書感想文は、どれも素晴らしい内容でした。
そして、「自分の思いをテーマ」に書いている共通点があります。
作品から得た感情から、自分の思いや考えでテーマを生み出すことは大変なことでもあります。
読書がきっかけで、物事を考える力を養う。
それは、大人になってからの方が役に立つことだと思いますよ。
読書感想文のお役立ちリンク
読書感想文の書き方と本選びの全て
www.yu-hanami.com
読書感想文を急いで書く2つのポイントと例題
www.yu-hanami.com
小説選びのポイント~小説選びは面白いと感じた本を手にとって
www.yu-hanami.com
実用書選びのポイント
www.yu-hanami.com
読書感想文におすすめの本〜2018年
www.yu-hanami.com
文章の書き方~文章の書き方を見直して、文章力を磨く取り組み まとめ
www.yu-hanami.com
